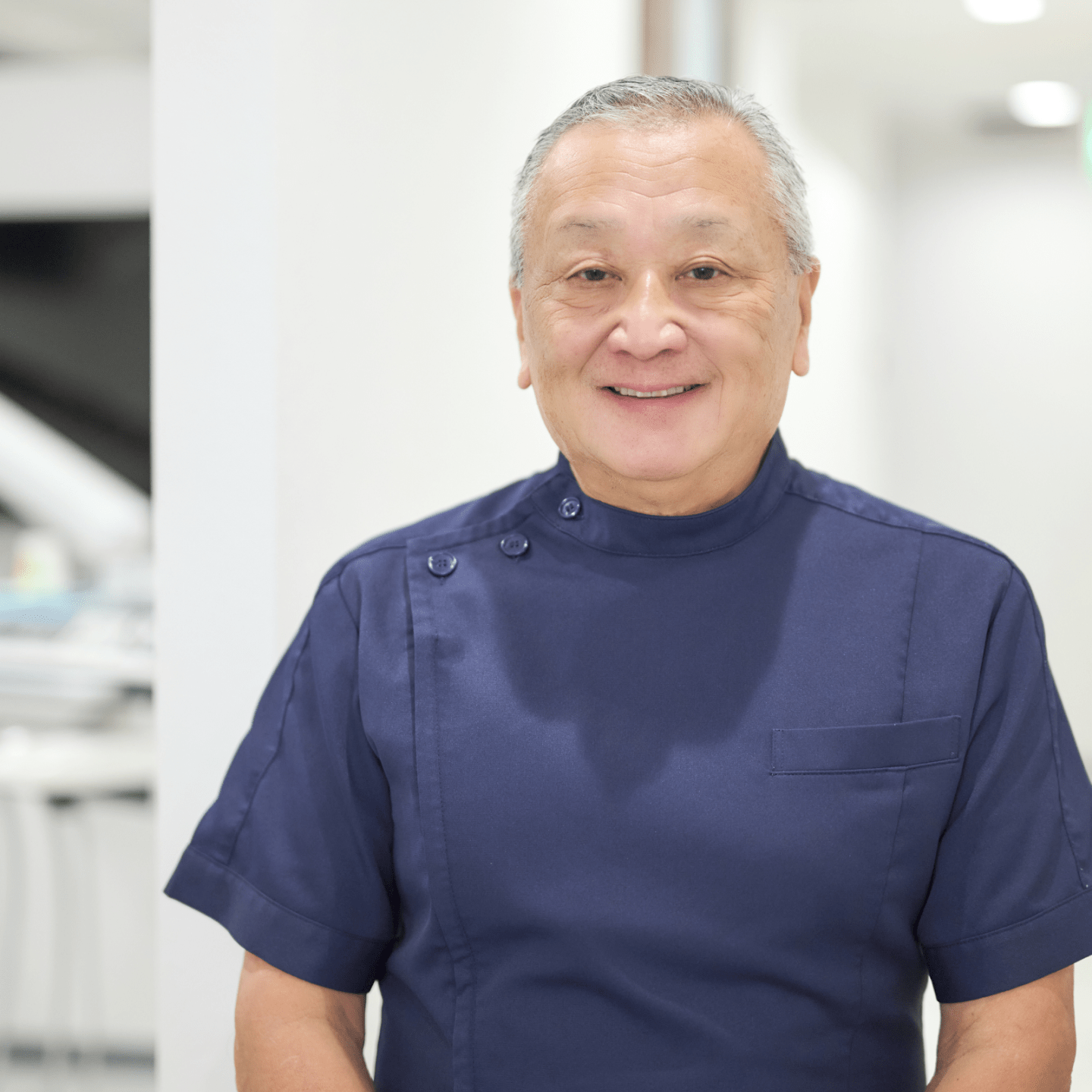「歯磨きはしっかりしているのに、虫歯や口臭が気になる……」
そんなお悩みの背景にあるのが、歯と歯の間の歯垢(プラーク)です。
この歯垢をしっかり除去するために、多くの歯科医がすすめているのが「デンタルフロス」。
毎日の歯磨きにプラスするだけで、歯周病や虫歯のリスクをグッと減らすことができます。
この記事では、歯科医師が、デンタルフロスの基本的な使い方や種類の違い、選び方、そして正しい習慣化のコツまでわかりやすく解説します。
デンタルフロスとは?

デンタルフロスは、歯と歯の間に入り込んだ歯垢(プラーク)や食べかすを取り除くためのケア用品です。
歯ブラシだけでは届かない部分をしっかり掃除することで、虫歯や歯周病の予防に役立ちます。
ここでは、なぜフロスが必要なのか、その役割や歯間ブラシとの違いについて詳しく見ていきましょう。
デンタルフロスの効果は?
デンタルフロスは、歯と歯の間に糸を通して歯の側面をやさしくこすることで、歯ブラシでは届きにくい「歯間部(しかんぶ)」の歯垢(プラーク)を効果的に除去できます。
特に、虫歯ができやすい歯間部の隣接面(歯と歯が接している部分)の清掃にすぐれており、定期的な使用により虫歯や歯周病の予防に役立つでしょう。
また、プラークを減らすことは歯肉炎の予防や口臭対策にもつながりますよ。
歯ブラシだけでは不十分な理由
どれだけ丁寧に歯を磨いていても、実は歯ブラシの毛先が届かない場所があります。
とくに「歯と歯の間(歯間部)」は、歯ブラシだけでは磨き残しが起こりやすく、歯垢がたまりやすい部分です。
実際、歯ブラシだけで落とせる歯垢は全体の約60%といわれています。
残りの約40%をカバーするためには、デンタルフロスや歯間ブラシといった補助的な清掃用具の併用が虫歯や歯周病予防(※)に効果的です。
歯間ブラシとデンタルフロスの違い

歯間ブラシとデンタルフロスは、どちらも歯と歯の間をきれいにする道具ですが、対象となる歯間の広さや使い方に違いがあります。
| 項目 | デンタルフロス | 歯間ブラシ |
|---|---|---|
| 使用目的 | 歯と歯の接触部分の汚れを落とす | 歯と歯のすきまの汚れを落とす |
| 適した歯の状態 | 歯と歯のすきまが狭い人向け | 歯と歯のすきまが広い人向け |
| 汚れを落とせる範囲 | 歯と歯がピッタリ接している歯間部 | 歯肉の近く、広めの歯間部や奥歯など |
| 清掃方法 | 糸で歯の側面をこする | ブラシで歯間を出入りせる |
| 推奨される使用頻度 | 1日1回、就寝前の使用が理想 | フロスト併用して週数回がおすすめ |
どちらが良いというわけではなく、歯の状態や目的に応じて使い分けることが大切です。
歯科医院でアドバイスを受けると、より自分に合ったケア方法が見つかりますよ。
デンタルフロスの正しい使い方

歯と歯の間は、歯ブラシだけでは磨き残しが発生しやすい場所です。
正しくフロスを使うことで、虫歯や歯周病のリスクを下げ、口内を清潔に保つことができます。
ここでは、デンタルフロスの基本的な使い方や注意点について解説します。
基本の使い方(指巻きタイプの場合)

デンタルフロスにはさまざまな種類がありますが、最も一般的なのが「ロールタイプ(指巻きタイプ)」です。
以下の手順で使用します。





力を入れすぎると歯ぐきを傷つける可能性があるため、ゆっくりと優しく挿入・清掃することが大切です。
「のこぎりを引くように優しく動かしながら挿入し、歯のカーブに沿わせて上下に動かす」のが基本の使い方です。
使うタイミングと頻度
デンタルフロスは1日1回の使用が推奨されています。
特に就寝前の歯磨き後に使うことで、夜間の細菌の増殖を抑え、むし歯や歯周病の予防につながります。
就寝中は唾液の分泌量が減り、細菌が繁殖しやすい環境になるため、口腔内を清潔に保ってから眠ることが大切です。
また、食べ物が挟まったときや違和感を覚えたときに都度使うのも、口腔ケアとして有効ですよ。
はじめてのフロス!気をつけたいポイント
歯の間の汚れをしっかり落とすために欠かせないデンタルフロス。
でも、初めて使うときは「痛くない?」「血が出たらどうしよう…」と不安になることもあるかもしれません。
ここでは、初心者がつまずきやすいポイントと、その対処法をわかりやすくご紹介します。
歯ぐきから血が出る場合
「フロスを使ったら血が出た」「うまく入らない」「糸が引っかかる」など、こうした声は、初めてのフロスでよく聞かれます。
これらは多くの場合、歯ぐきに炎症があるサイン。歯と歯の間に汚れがたまっていることが原因なこともあります。
フロスをやめるのではなく、正しい方法でフロスを続けていくと、数日で出血が治まることがほとんど。
ただし、強く押し込んだり、歯ぐきを傷つけるような使い方は避けてください。
怖がらず、やさしくケアを続けてみましょう。
フロスは「のこぎりを引くように優しく動かしながら挿入し、歯のカーブに沿わせて上下に動かす」のが基本です。
フロスがすぐ切れてしまう
何度もフロスが切れてしまう場合は、詰め物や被せ物の段差、または虫歯の可能性も考えられます。
無理に引き抜こうとすると、フロスがちぎれて残ってしまうこともあるため、ゆっくり前後に動かしながら取り除くようにしましょう。
無理に使い続けるのはNGです。
頻繁に同じ場所で引っかかる場合は、歯科医院でチェックを受けることをおすすめします。
被せ物・矯正中の注意点
被せ物やブリッジがある箇所、矯正中のワイヤーや装置がついている箇所では、通常のフロスが使いにくいことがあります。
無理に通そうとすると、補綴物(ほてつぶつ)を傷つけたり、装置が外れる原因になることもあるため注意が必要です。
そのような場合は、「スーパーフロス」や「フロススレッダー」といった専用の補助道具を使うと、安全かつスムーズにフロスを通すことができます。
矯正治療中の方は、歯科医師や歯科衛生士の指導のもとで適切なケア方法を身につけることが大切です。
使いやすいフロスを選ぼう
「指に巻くタイプはうまく使えない……」という方もご安心を。
そんな場合は、持ち手のついた「ホルダータイプ(Y字型・F字型)」を試してみるのもおすすめです。
フロスは、最初は使いづらく感じるかもしれませんが、「スッキリ感がやみつきになった!」という声も多く、毎日のケアに取り入れる価値は十分あります。
焦らず、少しずつ習慣にしていきましょう。
デンタルフロスの種類と選び方

デンタルフロスにはいくつかの種類があり、使いやすさやお口の状態によって、向いているタイプが異なります。
ここでは、代表的な種類とその特徴、選び方のポイントを詳しく解説します。
糸巻きタイプとホルダータイプの違い
デンタルフロスには、大きく分けて「糸巻きタイプ」と「ホルダータイプ(柄つき)」があります。
- 糸巻きタイプ
-
自分の指にフロスを巻きつけて使うタイプで、歯と歯の間にしっかりフィットさせやすいのが特徴です。
細かい操作ができるため、慣れると奥歯の間までしっかりケアできます。
- ホルダータイプ
-
持ち手がついていて、初めて使う方にも操作しやすいのがメリットです。
Y字型は奥歯に、F字型は前歯に使いやすい形状になっており、手先が不器用な方やお子さまにもおすすめです。
ワックスあり・なしの違い
フロスの糸自体にも「ワックスあり」と「ワックスなし」の違いがあります。
- ワックスありタイプ
-
表面に滑りをよくする加工が施されており、歯と歯の間にスムーズに入りやすいのが特徴です。
初心者や、歯の隙間が狭い方に適しています。
- ワックスなしタイプ
-
摩擦が大きいため、プラーク(歯垢)をしっかり絡め取る力に優れています。
フロスに慣れている方や、しっかり汚れを取りたい方向きです。
どんな人にどのタイプが向いている?
どのフロスが合っているかは、歯並びや手の器用さ、目的によって異なります。
指を使う細かい作業が苦手な方や、外出先でも気軽に使いたい方にはホルダータイプが向いています。
一方、歯のすき間が狭く、より密着した清掃がしたい方には糸巻きタイプが適しているでしょう。
また、フロスが歯に入りにくいと感じる方にはワックスありを、しっかり汚れを落としたい方にはワックスなしを選ぶとよいでしょう。
迷ったときは、歯科医院で自分に合ったフロスを相談するのが安心です。
デンタルフロスでよくある質問(FAQ)

デンタルフロスを初めて使う方や、使い慣れていない方から寄せられる質問に、歯科医師の視点からわかりやすくお答えします。
まとめ:毎日のフロス習慣で歯の健康を守ろう

デンタルフロスは、歯と歯の間に残った食べかすや歯垢(プラーク)をしっかり取り除くために欠かせないケアアイテムです。
歯ブラシだけでは落としきれない汚れにアプローチすることで、虫歯や歯周病の予防に大きく貢献します。
最初は慣れないかもしれませんが、1日1回のフロス習慣を続けることで、歯の見た目だけでなく、口臭予防や将来的な治療リスクの軽減にもつながります。
お口の状態は人それぞれです。デンタルフロスの選び方や使い方に不安がある方は、ぜひ一度歯科医院に相談してみてください。