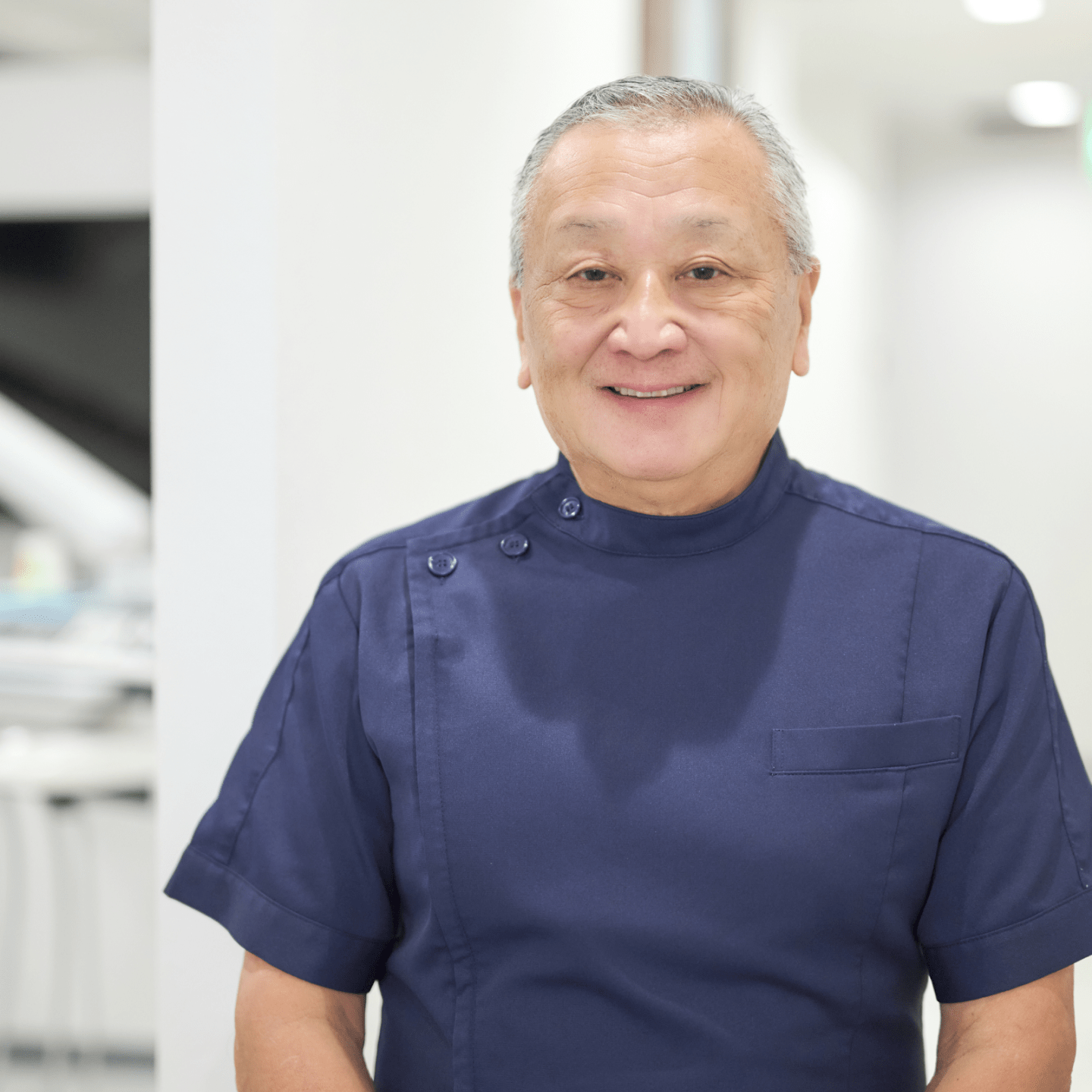「受け口」とは、下の前歯やあごが上の前歯より前に出ている状態のことを指し、「反対咬合」や「下顎前突(かがくぜんとつ)」とも呼ばれます。
見た目だけでなく、噛み合わせの不具合によって発音のしにくさや、顎関節への負担、虫歯・歯周病リスクの増加など、さまざまな問題を引き起こす可能性があります。
子どもの場合、早期に治療を始めると負担が少なく、成人でも矯正や外科手術で改善可能です。
本記事では、受け口の原因や症状、矯正治療の流れ・期間・費用・保険適用の条件までを歯科医がわかりやすく解説します。
【ミライデンタルクリニック】反対咬合歯列矯正の症例案内
ブルーライン
反対咬合(受け口)の歯列矯正



下の歯が上の歯よりも前にでる反対咬合です。
また、市の歯には若干の隙間も見られます。





表側(唇側)ワイヤーとマウスピースで、反対咬合が改善し、下の歯の隙間も無くなりました。
治療内容
表側(唇側)ワイヤー矯正(両顎)10カ月+マウスピース3ステップ
上下共に、歯の表面にブラケットを装着し、ワイヤーを通すワイヤー矯正を10か月実施。マウスピースを使用して最後の微調整を行いました。
治療期間
12ヶ月
施術の来院回数
11回
費用
550,000円(税込)
内訳:矯正治療495,000円(税込)・調整費55,000円(5,500円×10回)
※モニター価格
副作用とリスク
- 非常に稀なケースですが、金属アレルギーが生じる場合があります。
- 歯に接着されたブラケットが、歯から外れる場合があります。
- ブラケットに装着したワイヤーが一部外れる場合があります。
- 治療開始後、歯が動くことによって痛みを感じる場合があります。(通常は数日で治まります)
- シミュレーション結果とは異なる場合がありますが、治療しながら調整していきます。
- 歯列矯正治療の完了後、歯が元の状態に戻る場合があります。(後戻り)
【価格に自信!ミライデンタルクリニックの矯正治療費】
- インビザライン・コンプリヘンシブ:770,000円
- 表側ワイヤー矯正:660,000円(モニター価格:495,000円)
- 裏側ワイヤー矯正:660,000円(モニター価格:495,000円)
※ワイヤー矯正は、調整費5,500円/回、インビザライン矯正は、検査費用33,000円と調整費5,500円/回がかかります。
▷料金案内詳細はこちらの「料金について」ページをご覧ください。
ミライデンタルクリニックでは、事前の不安や疑問に丁寧にお答えする無料カウンセリングを実施中。
治療の流れや費用、後悔しないためのポイントも、専門スタッフがしっかりご説明いたします。
2026年2月1日からワイヤー矯正治療の価格が改定となります。
詳しくは、以下のブログでご確認ください。

受け口(反対咬合・下顎前突)とは?

受け口(うけぐち)とは、下の前歯が上の前歯より前に出ている噛み合わせの状態を指します。
歯科用語では「反対咬合(はんたいこうごう)」や「下顎前突(かがくぜんとつ)」と呼ばれ、不正咬合の一種です。
- 反対咬合(はんたいこうごう)
-
反対咬合は歯の位置(歯列)のズレによって起こる歯並びの問題。
- 下顎前突(かがくぜんとつ)
-
下顎前突は骨格的に下あご(下顎骨)が前に出てしまう構造的な問題。
通常、奥歯をしっかり噛み合わせたとき、上の前歯が下の前歯を2〜3mm程度覆うのが正常な歯並びとされていますが、受け口ではその関係が逆になってしまっています。
どちらのタイプも見た目の印象の変化だけでなく、噛む力のバランスの乱れや発音障害、さらには顎関節への負担にもつながるため、早めの対応が重要です。
受け口としゃくれの違い
「受け口」と「しゃくれ」は混同されやすい言葉ですが、厳密には異なります。
- 受け口
-
あくまで上下の歯の噛み合わせの問題で、下の前歯が上の前歯より前に出ている状態。
- しゃくれ(下顎前突の骨格性の問題)
-
下あごの骨が前に突き出ていることで起こる見た目の特徴。
つまり、「しゃくれ」は見た目の印象に使われる言葉であり、「受け口」は実際の噛み合わせの状態を示す歯科用語です。
両者が重なる場合も多くありますが、「しゃくれ=受け口」とは限らない点に注意しましょう。
見た目も噛み合わせも気になる場合は、早めに専門医に相談するのがベストです。
受け口の原因は遺伝?

受け口の原因は、遺伝だけではありません。
もちろん親からの骨格的な特徴を受け継ぐケースも多いですが、それだけでなく、日常の習慣や癖、成長過程での口腔内の変化が関係することもあります。
ここでは、主に2つのタイプに分けて受け口の原因を見ていきましょう。
【先天的】骨格や遺伝、歯性による受け口
受け口の多くは、骨格的なバランスの乱れに起因します。
たとえば、以下のような場合です。
- 下顎の骨(下顎骨)が前に成長しすぎる
- 上顎の骨(上顎骨)の成長が不十分
こういったことが重なると、下あごが前方に出てしまい、受け口になります。
さらに、歯に関連する要因もあります。
- 生まれつき歯の数や形に異常がある
- 上顎の歯が不足、下顎の歯が過剰に大きいなど
歯性受け口では、生まれつき歯の数や形に異常があり、歯並びが影響を受けることがあります。
また、親や祖父母も受け口だったというようなケースでは、骨格や歯の特徴が遺伝している可能性があります。
成長期の子どもの場合、特にこの骨格バランスの影響が大きく出やすいため、早期のチェックが重要です。
【後天的】子供の頃の習慣が引き起こすケース
遺伝的な要素がない場合でも、日常の習慣や癖が原因となって受け口になるケースもあります。
たとえば、以下のような習慣があると、あごの成長に偏りが生じたり、歯並びのバランスが崩れることがあります。
- 舌で下の前歯を押す癖(舌癖)
- 頬杖をつく癖
- 口呼吸
- 下の歯で上唇を噛む癖
- うつぶせ寝や横向き寝が多い
また、乳歯が早く抜けたり、虫歯で噛み合わせが崩れてしまうのも要因の一つ。
成長期の子どもはとくに影響を受けやすいため、生活習慣の見直しと定期的な歯科検診が大切です。
受け口を放置するとどうなる?見逃せないリスクとは

「受け口くらい、気にしなければいいかも」と思ってしまう方もいるかもしれません。
しかし、受け口を放置すると、見た目以上に深刻なトラブルに発展する可能性があります。
歯並びや発音、さらには将来的な健康面にも影響を及ぼすことがあるため、早期の対策がとても大切です。
噛み合わせや口呼吸の影響
受け口は、上下の前歯が正しくかみ合っていない状態です。
そのため、以下のような問題が起こりやすくなります。
- 奥歯・前歯への過剰な負担
→ 歯のすり減りや破折のリスクが増加。 - 虫歯・歯周病のリスクが上がる
→ 受け口が原因で口呼吸になりやすく、乾燥し細菌がたまりやすい状態に。 - 下顎の過成長・顎のズレ
→ 噛み合わせのずれが長く続くと、骨格バランスが崩れ顎関節症のリスクも。
- 食べにくさ・噛みにくさ
→ 噛み合わせが合わないことで、食事に時間がかかったり、咀嚼効率が悪くなることも。
こうしたトラブルは、放置すればするほど悪化してしまうことがあります。
「歯並びがちょっと気になるな……」という段階で早めに相談することが、将来の歯や顎の健康を守る第一歩です。
見た目や発音への影響
受け口は、口元の印象や話し方の明瞭さにも大きく関わります。
特に、以下のような点が気になってしまう方が多いです。
- しゃくれたような顔つきになる
→ 横顔や正面からの印象に影響しやすい - 口が閉じにくくなる
→ 無意識に口呼吸になりやすく、口内乾燥の原因になることも - Eライン(横顔の美しさの基準)が崩れる
→ 美容面で気にする方が多いポイント - 「さしすせそ」などの発音が不明瞭になる
→ 会話やプレゼン時に聞き返されることもあり、ストレスに
このような外見的・機能的な悩みは、自己肯定感の低下や人前で話すことへの不安にもつながります。
早めに対策をすることで、見た目も話しやすさも改善され、自然な笑顔と自信を取り戻せるでしょう。

老後に困る可能性がある
受け口を放置したまま年齢を重ねると、咬む力のバランスが崩れたり、顎の不調が現れたりと、日常生活に支障をきたすリスクが高まります。
- 入れ歯が合わない
→ 噛み合わせのズレにより、入れ歯が安定しない可能性がある - しっかり噛めず、食事が楽しめない
→ 硬いものや繊維質の食品を避けるようになりがち - 消化不良や栄養不足につながる
→ 食事の偏りが身体全体に悪影響を及ぼすおそれも
さらに、顎関節症や筋肉の痛み(首や肩のこり)などの慢性的な症状が出ることもあります。
結果としてQOL(生活の質)の低下を招き、健康寿命を縮めるリスクにもつながるため、早期の対応が重要です
受け口を治療するメリット

受け口(反対咬合・下顎前突)は、見た目の印象だけでなく、咀嚼や発音、顎の動きといった機能面にもさまざまな影響を与える不正咬合です。
治療によって得られるメリットは想像以上に多く、人生の質(QOL)を高めるきっかけになることもあります。
見た目の改善で自信アップ
受け口は、横顔や口元の印象に直結する不正咬合です。
下あごが前に出た「しゃくれ顔」や、Eライン(美しい横顔の基準)からはみ出す口元に、見た目のコンプレックスを感じる方も少なくありません。
しかし、矯正治療で歯並びと噛み合わせを整えることで、以下の変化が期待できます。
- フェイスラインがすっきりする
- 横顔のバランスが整いEラインも美しくなる
- 口が自然に閉じやすくなり、笑顔が引き立つ
「笑うのが恥ずかしい」「写真を撮るのが苦手」そんな悩みが改善されると、人前で話す自信が持てるようになり、恋愛や仕事への前向きな姿勢にもつながります。
とくに思春期の子どもや、第一印象が重要な社会人にとっては、見た目の変化が心理的な安心感をもたらす大きなきっかけになるでしょう。
機能的な問題の解消
受け口は見た目の問題だけでなく、機能面にも悪影響を及ぼしますが、正しい治療により、正しい噛み合わせに整えることで機能的な問題を解決できます。
- 噛みやすくなる:食べ物をしっかり噛めるようになり、消化がスムーズに。
- 胃腸への負担軽減:食べ物をきちんとすりつぶし、胃腸の負担を減らすことができる。
- 歯の保護と健康維持:咀嚼力が均等に分散されることで、歯のすり減りや歯周病のリスクを軽減し、顎関節への負担も軽減できる。
- 発音が改善される:正しい噛み合わせによって発音が明瞭になり、コミュニケーションがスムーズに。
将来の歯や顎にかかる負担を軽減できるでしょう。
治療を通じて、より健康で充実した生活を送れるようになります。
受け口の治療方法

受け口の治療は、年齢や症状の程度によって方法が異なります。
成長期の子どもと骨格が完成した大人では、アプローチも変わってきます。
ここでは子どもと大人、それぞれの治療法に加え、近年注目されているマウスピース矯正についても紹介します。
子どもの場合

子どもの受け口は、成長を利用して骨格のバランスを整えることができるため、比較的軽い治療で済む可能性があります。
子どもの受け口治療では、あごの成長をコントロールする「機能的矯正装置」を使い、上あごの発育を促したり、下あごの前方への成長を抑えたりするアプローチが行われます。
使用される装置には、取り外しが可能なマウスピース型の「プレオルソ」や、あごを引っ張る力を加える「フェイスマスク(上顎前方牽引装置)」などがあります。
こうした治療は、早ければ6歳ごろからスタートできることもあり、乳歯から永久歯への生え変わりを見ながら、第2期治療(ワイヤー矯正など)へと移行可能です。
成長期のうちに適切な治療を受けることで、見た目や機能の改善だけでなく、将来の大がかりな治療を予防することもできます。
早期発見と適切なタイミングでの対応が、子どもの歯並びと健康のためのカギです。
大人の場合

大人の場合、成長が止まっているため、骨格の成長を活かすことはできません。そのため、歯の位置の調整に加え、骨格へのアプローチが必要になることがあります。
大人の受け口治療には、一般的に表側または裏側のワイヤー矯正が使用されます。
軽度の受け口であれば、取り外し可能で目立ちにくいマウスピース矯正(インビザラインなど)が適用されることもあります。
しかし、骨格に大きなズレがある重度の受け口では、矯正治療だけでは改善が難しいため外科手術(外科矯正)を併用する必要がある場合もあります。この場合、矯正歯科と口腔外科が連携し、噛み合わせと見た目の両方を改善します。
外科矯正は、条件を満たせば保険適用になることもありますので、費用が心配な方には事前にカウンセリングを受けることをおすすめします。


治療にはどれくらいの期間と費用が必要?

受け口の治療は、歯並びや骨格の状態によって必要な期間や費用が変わります。
ここでは、治療にかかるおおよその目安を紹介します。
矯正治療の期間
受け口の矯正治療には、1年〜3年程度の期間がかかるのが一般的です。
ただし、症状の重さや選ぶ治療法によって大きく異なります。
| 治療法 | 治療期間の目安 |
|---|---|
| マウスピース矯正(軽度) | 約1〜2年 |
| 表側ワイヤー矯正(中等度) | 約2〜3年 |
| 裏側ワイヤー矯正 | 約2〜3年 |
| 外科矯正(骨格のズレが大きい場合) | 約半年〜1年(+術前後の矯正あり。約2〜3年) |
骨格性の受け口(下顎前突)で外科的処置を併用する「外科矯正」のケースでは、手術前後の矯正も含めて治療期間が長くなる傾向があります。
外科手術自体は半年〜1年程度ですが、術前矯正や術後矯正の期間を含めるとトータルで3年〜5年以上かかることも少なくありません。
治療費の目安
受け口の治療費は、選ぶ矯正方法や症状の重さによって大きく異なります。
一般的な自由診療の場合、以下のような目安となります。
| 治療法 | 費用の目安(自由診療) |
|---|---|
| マウスピース矯正(インビザラインなど) | 約70〜100万円 |
| 表側ワイヤー矯正 | 約80〜100万円 |
| 裏側ワイヤー矯正 | 約100〜130万円 |
| 小児矯正(1期治療) | 約40〜60万円 |
| 外科矯正(保険適用あり) | 約30〜65万円(保険適用の場合) 約100〜300万円(自由診療の場合) |
たとえば、外科矯正の場合は顎変形症と診断されれば保険適用になることもあります。
費用については、医療機関によって幅があります。また、分割払いやデンタルローンに対応しているところも多いため、無理のない範囲での治療が可能です。
まずはカウンセリングで、総額の見積もりをしっかり確認しておくことが大切です。
まとめ:受け口を治して理想の歯並びを手に入れよう!

受け口は、見た目だけでなく、噛み合わせ・発音・顎関節など、日常生活のさまざまな場面に影響を及ぼす可能性があります。
放置していると、将来的には歯や顎へのダメージが大きくなり、治療が困難になるケースも少なくありません。
ですが、早期に正しい知識を持って対応すれば、矯正だけで十分に改善できることも多いです。特に子どもの場合は、成長を活かした治療ができるため、負担も少なく済むことがあります。
大人になってからでも、治療方法の選択肢は豊富にあります。見た目に配慮したマウスピース矯正や、必要に応じた外科矯正も含めて、ライフスタイルに合った方法を選ぶことが大切です。
まずは、「治療するかどうか」ではなく、「現状を正しく知ること」から始めてみませんか?